| ● 裁判官に職員の勤務評定権を −現実的で建設的な司法政策論争のために |
| 浅見宣義(大分地方裁判所) |
☆ この拙稿は,1998年度(平成10年度)日本法社会学会学術大会ミニシンポジウムI「構造変容と司法改革」(名古屋大学)において,私が報告した内容をまとめたものである。法社会学会の当時の雑誌に掲載していただいた。8年前のものではあるが,現在の公務員制度改革,特に、新たな人事評価制度(国家公務員について,平成18年1月から新たな人事評価の試行が行われている。)構築の波が,裁判所にも押し寄せている中で,「誰が評価するのか」という基本的な枠組みを考えるについて,8年前の拙稿が参考になると思い,掲載する次第である。現在の動きについての,私見は「Judgeの目その12」をご覧いただきたい。 一 構造変容と司法の受容 現代は、構造変容の時代といわれ、日本社会のシステムが大きく変わろうとしている。我が司法部にもそうした認識は十分にある。例えば、最高裁長官の施政方針演説ともいうべき今年の「新年の言葉」(裁判所時報1209号)には、「自律的な個人を基礎としつつ、より自由かつ公正な社会」への転換で、司法への期待が高まっていることが強調されている。こうした構造変容を受けて、司法は、民訴法の改正や訴訟運営の改善、司法試験と法曹養成制度改革の他に、「裁判部門の充実強化」という対応をしている。総務や会計といった事務局部門ではなく、裁判をする「裁判部門」の人的・物的・制度的充実を図ろうとするものである。その内容は、司法の予算に如実に現れている。司法予算は、平成9年度約55億円増、同10年度約56億円減で、追い風があるのに横這いであるが、その中で一際目立つのが、「裁判部門」を構成する書記官の増員であり、各年度150名、250名と大幅増である。裁判官の増員は各年度20名であるから、裁判官の増員ではなく、書記官の増員によって「裁判部門」を充実強化するのが今の流れであろう。 二 「裁判部門」充実強化の理論的支柱 この流れを支えるのが「裁判官と書記官の協働体制」「書記官のコートマネージャー化」という理論である。「裁判官と書記官の協働体制」は、裁判をする裁判官と、公証官である書記官(さらには、速記官や事務官も)を、事件の解決という共通の目標下にチームワークで有機的に連携させ、裁判部の執務能力を高めるという理論である。そして、右連携のために、書記官の仕事を調書作成事務から進行管理事務へシフトするのが「書記官のコートマネージャー化」という理論である。この2つの理論は、司法外ではあまり聞かないが、司法の内部では毎日のように繰り返されている。 ただ、この理論は、実は「司法政策」なのだと強調された方がおられる。高名な加藤新太郎前司法研修所事務局長(現東京地裁部総括判事)であり、書協会報140号に「裁判所書記官役割論の基礎ー裁判所書記官と裁判官の協働とは何かー」という講演録が掲載されている。加藤前局長は、「協働」は本質ではなく、司法政策であると言われている。そして、このような政策が採られる基礎として、事件増、訴訟機能の向上の要求、書記官の資質の向上、書記官のモチベーション管理という4つを挙げ、政策である以上、政策的基礎があり、検証によって評価が決まり、変更可能性があると明言されている。おそらく、現在の文献の中で、2つの理論の背景や本質を最も的確に述べられたのが加藤講演録である。 では、政策だとして、その政策は支持されるべきであろうか。私は、支持されるべきであると思う。この政策は、司法が現実に保有する人的基盤、能力を前提にし、司法に対する需要の量的、質的アップに対応しようとする現実的政策である。また、司法内部で積み重ねられた要望の歴史(書記官への権限委譲、書記官の待遇改善等)に沿ったものであるし、結果として、この司法政策で、書記官層の活性化は目を見張るものがある。そのため、裁判所の事件処理能力は確実に高まっている。いつ、どこで、誰が、どういう手続で決定した司法政策か不明であるという問題は残るし、裁判官の増員論の足を引っ張る役割を果たしてはいけないが、内容が評価できる以上支持し生かしていくべき政策と思われる。 しかしながら、この政策には、一つの見過ごせない欠点がある。それは、「協働」といいながら、チームをまとめる裁判官の法的権限の裏付けが不十分であり、また「書記官のコートマネージャー化」として、裁判官の仕事を一部委譲したのに、裁判官が書記官を制御する権限が不明確なことである。この政策がソフトなもので、そうした管理的な面は捨象して考えているのだとか、政策だから、成功していけば次の段階で出てくのだという意見も理解できるが、おそらくこの政策は後戻りできない性格のものであるから、成功が確実であるような対策をたて、きちんとした法的処理をし、裁判権の帰属の問題と調和させることも必要なのである。私は、それが裁判官による職員の勤務評定権であると考える。 三 裁判所の職員体制と指揮監督体系 現状では、各裁判官に職員の勤務評定権は認められていないようであり、そもそもどのような体系で勤務評定がされているかはっきりしない。ただ、勤務評定は、その名の如く、勤務内容を評定するものであるから、勤務の内容を決めたり命じたりする者、すなわち指揮監督権者が評定者になるのが望ましいし、少なくとも評定に関与することが最低限必要なのではなかろうか。これは、一般の国家公務員の場合、勤務成績の評定の手続及び記録に関する政令7条2項で、評定者は職員の監督者の中から選ばれることと合致する。 では、裁判所の指揮監督関係であるが、これがえらく複雑である。裁判所には、裁判官、書記官、事務官、速記官等多数の官職が存在し、複雑な組織形態をなしているからである。ただ、まとめると、裁判部職員に関しては、二重の指揮監督関係があるということになろう。一つは、(1)裁判官からの指揮監督であり、ア受訴裁判所からの事件についての命令(裁判所法60−4、60の2−3)と、イ部に属する裁判官の会議による監督(下級裁判所事務処理規則4。部の司法行政の分配を受けている。)がある。もう一つは、(2)首席書記官以下のラインによる指導監督であり、一般の執務についての指導監督(大法廷首席書記官規則3−3、5−3等)を内容とする。(1)アは裁判権に、(1)イ、(2)は裁判官会議による監督権(裁判所法80)に由来する(別紙)。そして、裁判所における指揮監督の特殊性は、司法行政的な指揮(指導)監督が、裁判官、裁判所書記官、裁判所速記官の権限に影響を及ぼし、またはこれを制限してはいけない(裁判所法80、大法廷首席書記官規則8)ことである。つまり、裁判の独立が中核にあり、(1)アが本来最も重視されるべき指揮監督となる。このような「本来」的性格の点はしばらく置くとしても、「裁判官と書記官の協働体制」「書記官のコートマネージャー化」という政策のもとでは、現実に事件を担当するときの指揮監督関係、すなわち(1)ア、そしてそれに近い(1)イが「政策的」にも重視されなければならないのではなかろうか。 しかしながら、現実の法制度としては、(2)について通達で具体化された監視(査閲、査察、検査)、調整・指示(訓令)・指導、諸施策の企画立案、注意、部の裁判官に対する意見申述等の権限に比し、(1)ア、イについては制度的に具体化はされていない。その結果、勤務評定も現実には(2)の具体化としてなされているようである。私は、(1)ア、イの具体化として裁判官による勤務評定権を位置づけることが必要と考える。そして、(1)アの具体化として、担当裁判官が、具体的事件を通じて、担当書記官の調書作成能力の外、裁判官との協働下でコートマネージャー的役割をどの程度達成できたかを評定することになる。(1)イの具体化として、裁判官室が、当該書記官の裁判官室と書記官室と連携に果たした役割、部の運営に果たした役割等を評価することになる。ただし、裁判官による職員の勤務評定は、(2)のラインによる勤務評定と両立する。(2)のラインによる勤務評定は、査閲、査察等の事項を評定するものとなろう。裁判官、裁判官室による職員の勤務評定と、首席書記官以下のラインによる勤務評定により、当該書記官や事務官を、多面的に評価していくことになり(多面的評価制度)、これが最も望ましい形態ではないかと思われる。 四 今何故勤務評定か ところで、今勤務評定、特に評定権者を問題にするのは、背景として構造変容の公務員社会への反映があるからである。具体的に言うと、公務員の社会が勤務評定に関する能力主義、実力主義に踏み出すという形で反映が進んでいるのである。これが裁判所にも押し寄せている。平成9年度の人事院による一般職の給与等についての報告は、従前の流れを進め、給与改定について「職員の職務を基本とし、能力と実績を重視したものへの転換を進めていくことが肝要」とし、具体的には、勤勉手当の成績率の幅を拡大すること、管理職員について、成績率の幅も一般職員よりも広げることの外、今後、勤務実績に応じた特別昇給制度の一層の活用や、弾力的な昇格管理の運用の検討を示唆している。この動きは、裁判所職員臨時措置法や裁判所職員に関する臨時措置規則で、裁判所にも反映するのである。その結果、裁判所でも今後ボーナスにさらに差がつくようになり、昇給、昇格で能力主義、実力主義が濃厚になり、年功序列的要素が後退していくであろう。こうした時代にあっては、職員の将来性や周囲との協調といった点もさることながら、現実に担当した職務についての成果、そしてそこに現れた能力に重点を置いて適正に勤務評定がされる必要があり、それは、書記官の作成した調書を見るだけでなくだけでなく、現実に進行管理の働きを受けて事件解決に役立てる裁判官による評価というものが必要不可欠なのである。今勤務評定、特に評定権者を問題にするのは大きな時代的背景もあることを強調しておきたい。 五 裁判官による勤務評定の効果と問題点 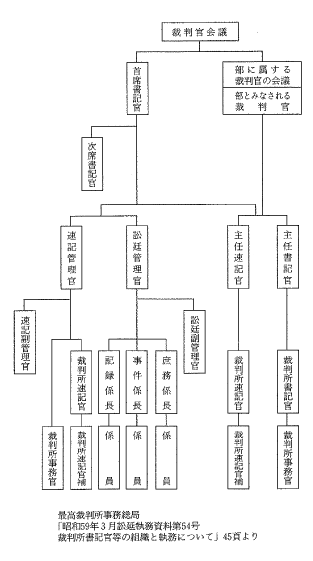 裁判官が職員の勤務評定をしていくことになれば、チームとしての有機的連携をさらに強めことになろう。進行管理等事件処理を通じた書記官の直接的、具体的な評価による書記官のモチベーション管理も進めることができよう。それらの結果、事件増、訴訟機能の向上の要求に今以上に対応することが可能になってくるのではないかと思われる。裁判官の側には、現状では十分とは言い難い「人を使う」「人を評価する」「人を育てる」ことに対する関心と能力を高めていく契機になろう。 裁判官が職員の勤務評定をしていくことになれば、チームとしての有機的連携をさらに強めことになろう。進行管理等事件処理を通じた書記官の直接的、具体的な評価による書記官のモチベーション管理も進めることができよう。それらの結果、事件増、訴訟機能の向上の要求に今以上に対応することが可能になってくるのではないかと思われる。裁判官の側には、現状では十分とは言い難い「人を使う」「人を評価する」「人を育てる」ことに対する関心と能力を高めていく契機になろう。しかしながら、裁判官が職員の勤務評定をしていくことになれば、問題点も当然ある。従前の司法行政の体系や運用を崩すのではないかという不安やとまどいが生じるであろうし、裁判官に勤務評定を行う能力は育つものなのか、多忙な裁判官の仕事の中で十分な評定作業はできるのか、書記官等職員からの拒絶反応があるのではないかといった前提条件についての問題が生じるであろう。また、チームワークというソフト路線から、勤務評定というハードな路線に向かうことが裁判部に緊張した関係を持ち込まないかという組織文化の問題もある。詳述はできないが、これらの問題点は克服していかなければならないものである。ただ、書記官の職務の独立性に対する配慮の点だけは性質の違うものとして常に意識しておかなければならないであろう。書記官は、裁判官の指揮監督下にあるといっても、公証権限(裁判所法60ー5のような権限もある。)や、裁判官の命を受けない独立の権限もあり、裁判官による勤務評定は、これら書記官の独立性を侵害するものであってはならないのである。 最後に、今回私が選んだのテーマは、司法内部の地味なテーマのような印象を持たれるであろう点に触れておきたい。地味な点は否定しないのだが、あえていうと、今の司法政策の延長線上にあって、現実的な政策論争の題材になりうるテーマなのである。そして、実務的能力と関心が中心の伝統的な職人的裁判官像(極めて勤勉で実直である。)から、司法行政能力も身につけた裁判官像への転換の契機になりうるのである。これは、将来、裁判官会議、常任(常置)委員会の復権や、分権的な司法の展望につながっていくであろう。 |
| 以上 |
| (平成18年6月) |